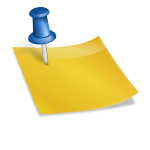一般社団法人とは?メリット・要件・税制・基金・必要書類を解説
更新日:2025年1月23日
◆もくじ◆
一般社団法人の基本をわかりやすく解説!
一般社団法人とは?
一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人で、人が集まって初めて法人格を取得することができます。
2名以上の社員が必要!
一般社団法人は、人が集ることによって法人格が与えられますので設立のための要件として、2名以上の人(社員)が必要になります。
※社員には、個人はもちろん、企業などの法人も就任できます。
なお、一般社団法人は、必ずしも「公益」を目的とする事業内容である必要はありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。
例えば、「収益」を上げることを目的としても、法人内部の「共益」を目的としても構いません。
また、法務局への登記のみで設立することができるため、さまざまな活動を行うための法人格として活用されることが予想されます。
一般社団法人の特徴
- 法人の活動内容は問われず、登記だけで設立が可能(準則主義を採用)
- 社員2名以上で設立ができる
- 設立時に有する資金・財産がなくても設立が可能
- 社員、社員総会及び理事は必置
- 理事会、監事、会計監査人を置くことができる
- 基金制度を設けることができる(定款での定めが必要)
- 原則課税と原則非課税の2種類の形態がある
一般社団法人と株式会社の違い
一般社団法人と株式会社の違いに焦点をあてると、以下のような特徴も出てきます。
- 登録免許税が安くなる
- 定款認証の際に収入印紙が不要
- 資本金という概念がないため、設立費用が少なくて済む
- 設立登記までの期間が短い(2週間~)
比較的小規模に設立したい方にはおすすめの法人形態です。
一般社団法人のメリット
メリット1:信用力の向上
メリット2:法人名義での契約等が可能
メリット3:自治体・行政機関の仕事が受けやすくなる
メリット4:法人税の優遇措置を受けられる場合がある
一般社団法人の機関
1.社員総会+理事
2.社員総会+理事+監事
3.社員総会+理事+監事+会計監査人
4.社員総会+理事+理事会+監事
5.社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般社団法人は定款定め方によって上記5パターンの機関設計が考えられますが、小規模な一般社団法人の設立ですと、1か2になるでしょう。尚、公益社団法人を目指す場合には、理事会の設置が必須ですので、3~5いずれかの機関設計になります。
一般財団法人とは?
一般財団法人は、一般社団法人と同じく平成20年12月からはじまった「新公益法人制度」により、設立できるようになった法人形態です。今までの財団法人とは異なり、団体の公益性や目的は問われず、一定の財産があれば誰でも設立することができます。
一般財団法人は、財産に法人格を与えるもので、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、財産の管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。
一般社団法人と一般財団法人の違い
一般社団法人と一般財団法人の違いは以下の通りです。
一般社団法人は、一定の目的のために社員の「活動」自体に重点を置くので設立時に有する資金・財産がなくても設立が可能です。
「基金」という制度がありますが、法人の任意、つまり基金制度を設けるか否かは自分たちで決められます。
一方、一般財団法人は、拠出された財産を一定の目的のために利用することに重点を置きます。
また、設立時に300万円以上の財産の拠出が必要になります。
一般財団法人の機関
1.評議員+評議員会+理事+理事会+監事
2.評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般財団法人は、理事会、評議員会を必ず置く必要があります。
設立者が1名以上、理事3名、評議員3名、監事1名の最低でも設立には7人以上は必要となります。
また、定款の定めにより、会計監査人を置くことができると任意ですが、 大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人)は、会計監査人を置かなければなりません。
一般社団法人の基金とは?
一般社団法人は、設立に際して財産の拠出を必要とはされていませんが、活動の原資となる資金調達の手段として、「基金制度」が設けられています。
「基金」とは、社員や社員以外の人から一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)に搬出された金銭その他の財産であって、当核一般社団法人が搬出者に対して法律、および当核一般社団法人と当核搬出者との間の合意の定めるところに従い、返還義務(金銭以外の財産については、搬出時の当核財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。
基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しながら、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。 基金は、基金の設置、非設置は法人が任意に定めることができ、絶対に必要なものではありません。
基金を設置する場合は定款にその旨の定めを置く必要があります。
一般社団法人の基金については、株式会社の資本金のように価額を登記する必要はありません。
しかし、登記上はそれで問題なくとも、誰がいくら(いくら相当の物)を拠出したのかなど明らかにするため、募集の手続きには書面のやり取りをする必要があります。
なお、基金制度を一度でも採用した場合、それを廃止することはできません。
基金募集手続きの流れ
1.社員総会(又は理事会があれば理事会)で募集事項を決定
→社員総会(又は理事会)議事録を作成
2.基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、募集事項等を通知
→基金募集通知書を作成
3.申込みをする者が基金申込書を提出
→基金申込書を作成
4.社員総会(又は理事会)で申し込みをした者の中から、 基金の割当て者(基金の引受人)とその額を決議
→基金割当通知書を作成
5.払込期日の前日までに、基金の引受人に対して割当額を通知
6.基金の引受人と契約書を交わす
→基金拠出契約書を作成
7.基金の引受人が法人の銀行口座へ基金の払込み、又は財産の給付を行う 基金の総額を引き受ける契約
※基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、上記2~5の手続きは不要となり、以下の手順のみで手続きは完了します。
1.社員総会(又は理事会があれば理事会)で募集事項を決定
2.基金拠出契約書を交わす
3.基金の引受人が法人の銀行口座へ基金の払込み、又は財産の給付を行う
基金の返還について
事業年度に係る貸借対象表上の純資産の額が基金等合計額を超える場合、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの期間に限り、その超過額を返還の限度額として、基金の返還をすることが可能です。※基金の返還に係る債権には利息を付けることはできません。
尚、基金を返還するには定時社員総会の決議が必要となります。
一般社団法人の税制・税金について
税務上は2通りに分かれる
- 営利型の一般社団法人
- 非営利型一般社団法人
前者の場合には全所得課税となりますので、株式会社等の営利法人と何ら変わらない課税方式を採用されます。
一方、後者の場合には、収益事業にのみ課税され、寄付金や会員からの会費収入等の共益事業に対しては非課税となりますので、税務上のメリットが大きいと言えます。収益事業から生じた所得に対する法人税率は30%、所得金額年800万円以下の金額は18%になります。
法人税の課税対象になる「収益目的事業」について
収益目的事業とされている以下の34事業から生じた所得に対しては、法人税が課税されます。
※ただし以下の34の事業に該当する場合でも、個別に非課税事業として認められる場合もあります。
詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保険業
- 技芸教授業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権の提供等を行う事業
- 労働者派遣業
非営利型法人になるには?
税金を節約できるメリットがある非営利一般社団法人となる為には、下記の要件を満たす必要があります。
- 主たる事業として収益事業を行わないこと
- 剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
- 過去に定款違反がないこと
新公益法人制度について
平成20年12月1日から公益法人改革三法が施行され、明治以来続いていた公益法人制度が全く新しいものに生まれ変わりました。
下記2つが特徴になります。
①従来の主務官庁(都道府県の場合は、知事、教育委員会等)による、要件の厳しい設立許可制度を廃止し、簡単な登記のみで法人が設立できるようになった。
②簡易な登記手続のみで設立することができる「一般社団法人」と「一般財団法人」という新たな法人形態が創設され、そのうち、公益目的事業を 行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者等による委員会(合議制の機関)の認定を受けることにより、それぞれ、「公益社団法人」、「公益財団法人」となることができるようになった。
公益認定を受けることのメリット
- 名称独占と社会的信頼性の向上
- 税務上の優遇措置
公益認定を受けることのデメリット
- 事業活動の制約
- 行政庁の指導監督
一般社団法人の設立要件
一般社団法人設立のための主な要件
- 一般社団法人設立の登記手続き
- 名称中に「一般社団法人」という文字を使用 (例「〇〇〇一般社団法人」「一般社団法人〇〇〇」)
- 社員は2名以上
※社員は株式会社などでもかまいません - 一般社団法人の定款は設立時の社員が作成、公証人の認証を受けなければならない
一般社団法人の「機関」についての主な要件
- 理事(任期は2年以内)を必ず置く
- 社員総会は必ず置く
- 一般社団法人の理事等は、社員総会の決議によって選任しなければならない
一般社団法人の「運営」「その他」についての主な要件
- 社員や設立者に剰余金、残余財産を受ける権利を与えてはいけない
- 行政に監督されることがなく、簡易な手続で設立が可能な代わりに、自主的、自立的な運営
- 事業年度毎の計算書類、事業報告等の作成、事務所への備え置き及び閲覧等による社員、評議員、債権者への開示
- 貸借対照表の公告
必要書類
- 定款
- 設立時社員の一致があったことを証する書面
- 設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
- 設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
- 設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
・就任を承諾したことを証する書面
・設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
(※ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く)
・設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面 - 印鑑証明書
- 登記すべき事項を記載したOCR用紙又は登記すべき事項を入力したフロッピー又はCD-R
- 一般社団法人設立登記申請書
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
一般社団法人・一般財団法人申請等のご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、これから一般社団法人を設立されるから、すでに一般社団法人を運営されている皆さまに対して、認証・認定に関する申請サポートや運営面での法務サポート、補助金申請等のサポートを行っております。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

専任スタッフが全国の案件を対応しております。