不動産業者必見!? 不動産取引の電子契約についてポイントを徹底解説!
投稿日:2025年4月14日
宅建業法の改正
近年の宅建業法の改正により、従来は紙ベースで行われていた不動産取引に関する契約手続きが、電子契約でも対応可能となりました。
不動産業界における業務効率化や、テレワーク対応など時代のニーズに合わせた大きな転換点といえます。

この記事では「重要事項説明書」や「契約書」の電子化において、実務上の取り扱いや注意点についてのポイントを改めて解説します!
改正の目的と意図
今回の宅建業法改正は、不動産取引におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するためのものです。
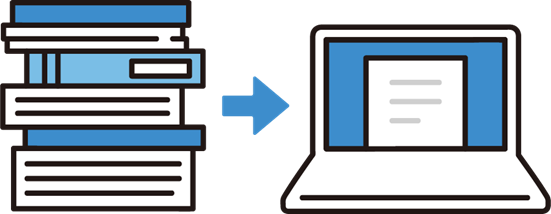
契約プロセスをオンライン化することで、取引の透明性と効率性を高め、不動産取引の利便性を飛躍的に向上させることが期待されています。
また、新型コロナウイルスの影響により非対面での契約ニーズが高まったことも、背景にあります。
不動産取引における電子契約利用が可能に!
2022年5月の法改正を受けて、賃貸借契約や売買契約など幅広い不動産取引において電子契約が正式に認められました。
これにより、契約当事者が場所を問わずスムーズに契約を締結できる環境が整備されました。
電子契約の導入により、書類の保管や管理の手間が削減され、業務効率の向上やペーパーレス化の推進にも貢献します。
ただし、法的効力や運用面でのルールを理解しておかないと、トラブルに発展するリスクもあるため注意が必要です。
そもそも電子契約とは?
電子契約とは、紙の書面ではなく、電子データによって契約書類を作成し、電子署名をもって合意を示す契約方法です。
従来のような紙の契約書への署名・押印を行う代わりに、クラウドサービスや電子署名ツールを用いて署名・認証を行います。

電子契約は「電子署名法」や「電子帳簿保存法」など、複数の法令に基づき法的な効力が認められており、正式な契約手段として利用可能です。
不動産業界では、重要事項説明書・契約書の電子交付が可能になったことで、取引全体を電子化できるようになり、大幅な効率化が期待されています。
重要事項説明への影響
書類の電子化
これまで重要事項説明書や契約書は書面での交付が義務づけられていましたが、法改正によりこれらの書類をPDFなどの電子データとして交付することが可能となりました。
ただし、電子交付を行う場合には、事前に相手方の同意を得る必要があり、電子データでの確認環境が整っていることが前提です。

また、データの改ざん防止や、長期保存が可能な形式での提供が求められます。
このような要件を満たすことで、電子交付でも法的な要件を満たす重要事項説明が可能になります。
押印義務の廃止
従来、不動産取引における契約書には実印の押印が求められる場面が多くありました。

しかし、電子契約の導入により、紙面への押印義務は原則として廃止され、電子署名がこれに代わる形となりました。
電子署名は、本人性の確認や改ざん防止に関して一定のセキュリティを有しており、法的効力も紙の署名・押印と同等です。
これにより、契約業務がオンライン上で完結できるようになり、物理的な印鑑の受け渡しや郵送作業が不要となります。
電子契約の注意点
電子契約は利便性が高い一方で、導入にあたってはいくつかの注意点があります。
・電子署名に対応したクラウドサービスの導入や運用体制の整備が必要がある。 ・電子契約を締結するためには、契約当事者双方が電子契約に対応できる環境を整えている必要がある。 ・契約書の改ざんやなりすましといったリスクに対応するために、信頼性の高い認証サービスを選定する。 ・電子帳簿保存法に基づいた適切な保存体制を構築する。 ・ITリテラシーの差によるトラブルを防ぐため、契約相手との事前確認や説明を徹底する。まとめ
不動産取引のデジタル化が進む中、2022年の宅建業法改正によって「電子契約」が大きな注目を集めています。
電子契約の導入は、業務の効率化・コスト削減・契約スピードの向上といった多くのメリットをもたらします。

しかし一方で、書類の電子化に伴うリスク管理や、法令遵守、契約当事者への配慮なども重要なポイントです。
本記事で解説した内容を参考に、電子契約導入に際しての疑問や不安を解消し、より安全かつスムーズな不動産取引を実現してください。
(著者:山本 羽乃)
